STEWBOSS interview
ALL I WANT TO DO IS SING MY SONG, SO SING A SONG, SING A SONG, SING A SONG

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
走るまえにしっかり歩きたい・・・
メジャーからのオファーはあるけれど、いまはまだその時期じゃない
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
|
こないだこのウェブ上で発表されたLAST HURRAH版『2004年トップ5アルバム』に、僕は大いに不満があるっ! だって僕のほかに誰も、このSTEWBOSSを挙げてくれていないんだから……という僕には「Marahが入ってないぞっ!」って声が聞こえてきそうですけど(笑)。
1999年に『Wanted A Girl』でデビューしたSTEWBOSSは、ニュージャージー出身のグレッグ・サーフェティを中心に、L.A.界隈で地味にキャリアを積んできたミュージシャンが集まってL.A.で結成。Miles of Musicから「シリアスじゃないカウンティング・クロウズ」と絶妙に評されたそのサウンドは、トム・ペティやスプリングスティーンのようなストレートなアメリカン・ロック・サウンドを軸にしながら、ミドル・テンポのフォーク・チューンから元気いっぱいのパワー・ポップ・チューン、しっとり泣きのバラードからドライヴするロックンロール・ナンバーまで、変幻自在に繰り出すバラエティの豊かさ(コネルズにも似てますね、と聞いたところ、あまり詳しく知らないと言ってました)。そりゃもちろん変化球主体のMarahのような器用さはないけれど、直球勝負を信条とする中堅アメリカーナ勢のなかで、やはりこの完成度の高さはズバ抜けていると認めないわけにはいかないのです。 昨年9月に3作目となる最新作『The Places We Meet』をリリースしたSTEWBOSS。もしもまだ聴いたことがないって人がいたら、是非聴いてみてください(CD BABYで購入できます)。LAST HURRAHを愛読されてるみなさんには絶対オススメですから。 今回は、そのメロディー・センスにますます磨きをかけた中心人物のグレッグ・サーフェティがインタビューに答えてくれました。音楽同様、にじみ出るオネスティが清々しくてたまりません。 ●最新作の『The Places We Meet』、とっても素晴らしかったです。僕の2004年ベスト・アルバム第2位に選ばさせていただきました!1位じゃなくてすみません……。売れ行きの方は好調ですか? 「うん、いい感じなんじゃないかな。今まででいちばんよく売れてるし、そうやって少しずつ成長していくのがいいんだよね。1作目よりも2作目、2作目よりも3作目っていうふうにね。“成長”っていうのはそういうことだから。2位だって全然構わないさ。君が1位に選んだティフト・メリットも素晴らしいからね。少なくともジョン・フォガティの上に選ばれただけでも光栄さ」 ●あなたはとても優れたメロディ・メイカーだと思うんですが、今回あなたがいちばん成長したと思うところはどんな点でしょうか? 「曲作りの面で成長したかどうかは正直言ってわからないな。たぶん成長してはいるんだろうけれど、それを自分で客観的に評価するのは難しいね。ただ、常に正直でいることだけは心がけているよ。それこそが曲にとっていちばん大切なことだと思っているからね。正直(honesty)であればこそ、そこに信じ得るもの(believable)や、真実味(truthful)、誠実さ(sincere)が表れてくると思うんだ」 ●ところで、STEWBOSSっていうバンド名の由来は? 「大学時代にヨーロッパに留学していた友達が、いわゆる売春宿に遊びに行ったときの話なんだけど……。彼らはそこを“Stew”と呼んでいて、そこのチャージにいた男は“Boss”と呼ばれていた。で、その男がちょっと年老いてしょぼくれた僕みたいだったんで、僕は彼らから“Stewboss”と呼ばれるようになってしまった。“pimp-daddy”(=ポン引き?)のちょっと古い言い方みたいなものかな。バンドを結成したときに、その懐かしいニックネームがしっくりきたんだ」 ●それでは、STEWBOSSならではの持ち味ってどんなところでしょう? 「STEWBOSSの歌は、僕たちの強い部分よりも、どちらかというと弱い部分から成っていて、そこがこのバンドの持ち味になっていると思う。多くのバンドは、自分たちが上手にできることばかりを奇麗に無難にやっているけれど、僕たちはもっと我武者らに奮闘していたいんだ。そうすれば、その歌には自ずと切迫した雰囲気とか、必死な想いが込められると思うしね。レコードを聴いてくれた人から、まるでこれが最後の演奏かのようだって言われることがあるんだけれど、僕自身いつもこれが最後だという想いで歌っている。それが秘訣だね」 ●あなた達は、セルフ・プロデュースとかセルフ・リリースというやり方にこだわりを持っていますか? 最近話題のブライト・アイズのコナー・オバーストも、いまだに地元オマハのローカル・コミュニティを大切にしていますね。インディペンデントでいるということは、あなた達にとってどれだけ重要なことなんでしょうか? メジャー・レーベルからのオファーだってあるんじゃないですか? 僕は絶対ジム・スコットにテープを送ってみるべきだと思うんですよ! 「ジム・スコットかぁ。いいね。それじゃ何か送ってみることにしよう。メジャー・レーベルに関しては、確かに何度かオファーを受けたことはあるけれど、いまはまだそういう時期じゃないと思うんだ。僕たちは皆、かつて在籍していたバンドなどを通じてメジャー・レーベルの経験があるから、今回はひとまず走るまえにしっかり歩き、歩くまえにしっかり這おうって決めたんだ。それこそひとりずつファンを増やしていくように、コツコツとキャリアを積んでいきたい。だから、決して反メジャーってわけじゃないけれど、現時点ではインディペンデントでいることはとても重要だね。なにより自分たちのペースでやっていけるし、バンドとしての自分達とはいったい何者なのか、言うべきことは何なのかっていうことがよくわかるからね」 ●あなたがテレキャスターを構えている写真を見たとき、真っ先にブルース・スプリングスティーンのことが思い浮かんだんですが、実際彼の大ファンだそうですね。彼のほかに、ソングライターとして、ヴォーカリストとして、あるいはギタリストとして影響を受けた人はいますか? 「それはもう挙げたらきりがないほどいるね。好きな理由もまちまちだし。ざっと挙げれば、ギタリストとしてはジミ・ヘンドリックスにカルロス・サンタナ、リンジー・バッキンガムにジミー・ペイジ。ソングライターだったらトム・ウェイツ、スモーキー・ロビンソン、キャロル・キング、それからなんと言ってもブルース・スプリングスティーン。ヴォーカリストとしては、僕とは似ても似つかないけれどレイ・チャールズとオーティス・レディング。ヴァン・モリソンやボノ、フィル・リノットあたりも大好きだね。このへんはちょっと似ていると思うんだけど」 ●そのブルース・スプリングスティーンが牽引して話題を呼んだ、こないだのVOTE FOR CHANGEツアーについてはどういう感想を持っていますか? 「いまアメリカが直面している問題について、彼が人々に議論する場を提供したことはとても素晴らしかったと思う。あまりヒート・アップしないでコンサート・フォーラムのようなかたちを保ったことにも意義があった。残念ながらアメリカは変革への票を投じなかったけれどね……。このところずっとアメリカは社会として分断されてきているけれど、僕たちはもういちどみんながひとつにまとまっていた頃のことを思い出すべきだ。実は今回のアルバム・タイトル『The Places We Meet』にもそういう想いが込められているんだ。僕たちはずっとお互いの相違点ばかりに目を奪われてきたけれど、いまはもっとお互いの共通点を探し始めるべき時なんじゃないかな」 ●あなたにとって、歌詞は曲よりも重要ですか? 僕も含めて、日本のファンがあなたの歌詞を細かいところまで理解することはなかなか難しいことなんですが、そういう人たちにも自分たちの歌をアピールできる自信はありますか? 「僕の場合はどちらかというと歌詞の方が重要かな。曲は歌詞をサポートして感情を高めてくれるものだね。でも、もしも曲を聴いただけでエモーションを感じ、心打たれたなら、必ずしも歌詞を理解する必要なんてないんじゃないかな。だからこそ僕は詩ではなく歌を書いているのさ。歌に宿るエモーションは普遍的で、言葉の壁など簡単に超えてしまう。そう、だから僕には日本のファンにもアピールできる自信はあるよ。本当に誠実な気持ちを伝えるのに、言葉を理解し合う必要なんてないんだ」 ●あなた達は「アメリカーナ」というジャンルに括られがちで、それはある意味あなた達の音楽がアメリカの音楽を象徴しているというふうにも捉えることができると思うんですが、あなた自身、自分たちがアメリカのバンドであるということを意識することはありますか? いまの時代、アメリカのバンドとして誇れること、あるいは誇りたいことなんてありますか? 「それはおもしろい質問だね。僕らが愛している音楽は、ブルース、ゴスペル、ロックンロール、ブルーグラス、カントリー、モータウン、ソウル……とすべてアメリカ音楽なわけだから、そういう意味じゃ僕らは紛れもなくアメリカのバンドということになるんだろう。でも、よくよく考えてみれば、これらはみんないろんな文化が混ざり合ってできたものだろ? ブルーグラスはフランスとイギリスからの移民の音楽が混ざり合ってできたものだし、ブルースだってアフリカやスペイン、イギリスの音楽が混ざったものだし、そうやって必ずどこか別の場所にルーツを遡ることができるんだ。だからこそアメリカの音楽は世界中あちこちで聴かれているんだと思うよ。あんまり質問の答えになってないかな……」 ●ずいぶんいろんな楽器を演奏してますけど、結構練習とかしてるんですか? 「本当はもっと練習しなくちゃいけないんだけどね。でも、僕がいろんな楽器を演奏しているのは、別に自分が得意だからというわけじゃなくて、単に他にやってくれる人がいないからなんだ。自分の頭のなかで鳴り響いたサウンドを実現してくれる楽器であれば、なんだって手に取ってしまうね。演奏できるかどうかなんて関係ない。欲しい音のためにだったら、なんとしてもやるさ」 ●名曲「Counting to 7 at Your Old Barstool」(前作『Sweet Lullabye』収録)が完成したときはどんな気持ちでしたか? あれは本当に名曲と呼ぶに相応しい曲ですね。 「それはどうもありがとう。でも、たいへん申し訳ないんだけど、書き終えたときのことはあんまりよく覚えてないんだ。ほとんどの曲はあっという間にできあがってしまうからね。僕は一曲完成させるのに何日も何週間もかけるようなタイプじゃないんだ。ほんの1時間くらいでできてしまうか、そうでなければとっくにあきらめて投げ出してしまうね。あの曲もパッとできあがってしまって、特に後になってどうこう考えたことはないな。そうやってみんなのいろんな反応を見るのは楽しいけどね」 ●最近、共感できるバンドっていますか? 「ダミアン・ライスやレイ・ラモンターニュ、ルセロあたりかな。彼らのうち誰かと一緒にツアーが出来たら最高だね」 ●では、あなたの2004年ベスト・アルバムを3枚ほど教えてください。 「レイ・ラモンターニュの『Trouble』、ザ・フィーチャーズの『Exhibit A』、ポール・ウェスターバーグの『Come Feel Me Tremble』だね」 ●ライヴでよく演奏する、お気に入りのカヴァー曲なんかも教えてもらえますか? 「弾き語りなら、トム・ウェイツの“Downtown Train”やボブ・ディランの“Shooting Star”、ニール・ヤングの“Everybody Knows This Is Nowhere”。バンド編成なら、ザ・バンドの“It Makes No Difference”やジム・クロウチの“Operator”、ウィスキータウンの“Excuse Me While I Break My Own Heart”。なんと言ってもいちばんのお気に入りはマーヴィン・ゲイの“Let's Get It On”なんだけど、これは自分の家でしか歌わないよ」 ●それでは最後に、これからの抱負を聞かせてください。 「将来自分が年老いてからも誇れる音楽を創り続けていきたい。そのことに尽きるね。おっとそれから……いつか必ず日本にも行きたいと思っているよ。それを言うのを忘れちゃいけなかった!」 (インタビュー◎高野匡哉) |
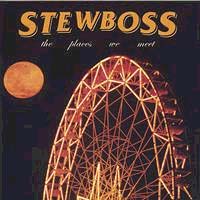
『The Places We Meet』 STEWBOSS (Stewsongs Records) |